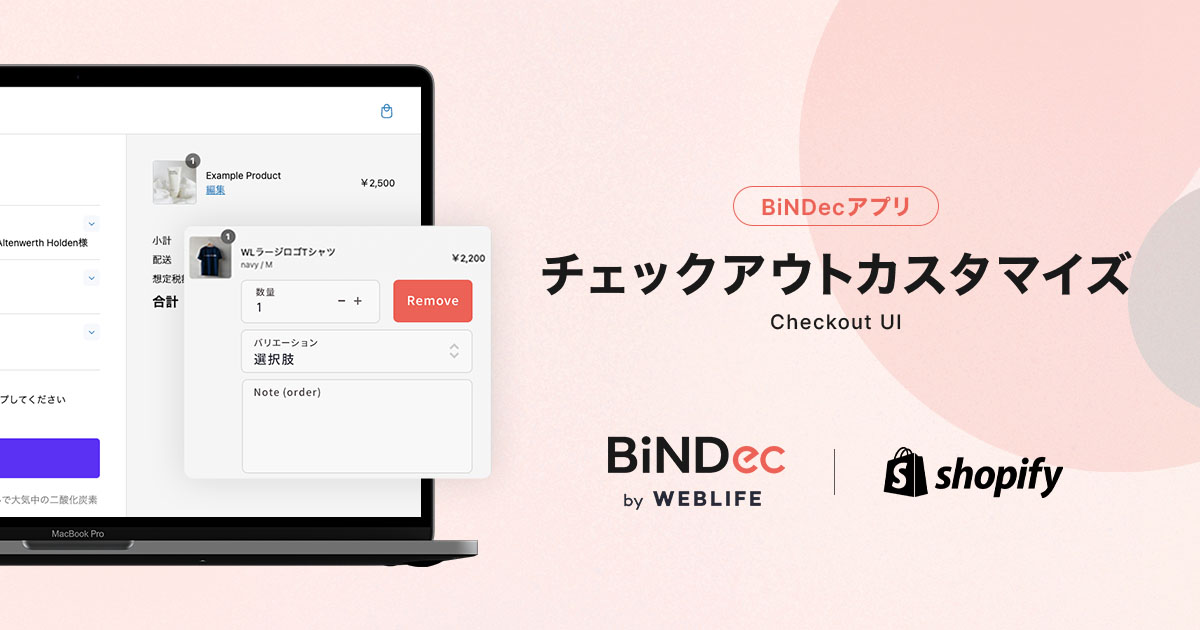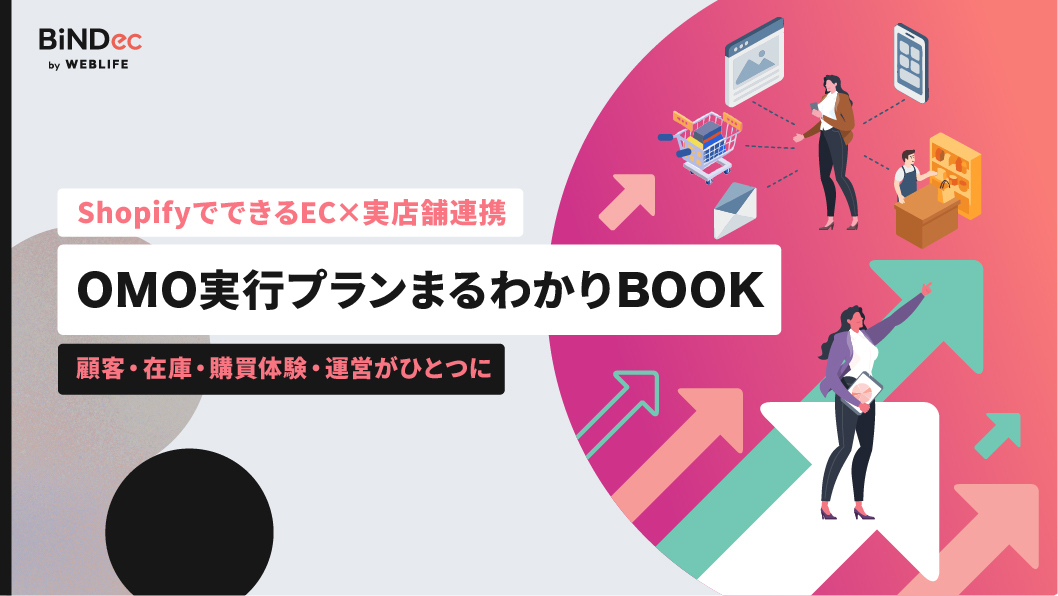ECサイトでは「返品トラブル」が、思わぬ信頼喪失や利益減につながりかねません。特にECプラットフォームのShopifyでは管理画面やアプリを活用して返品対応を柔軟に設計できるので、正しく活用することで、クレーム削減や信頼度アップにつながります。また、返品が起きてから対応するだけでなく、「そもそも返品を起こさない仕組みづくり」も重要な視点です。
この記事では、返品ポリシー作成の基本的なコツから、顧客対応を円滑にする実践的なテクニックまで、初心者でもすぐに活用できるノウハウをわかりやすく紹介します!
返品はリスクorチャンス?ECを取り巻く返品事情
ECサイトを運営する中で、なかなか避けては通れない「返品」。上手く対応できないと、単なる「売上のマイナス」ではなく、利益を大きく損ねることになりかねません。逆に上手くコントロールすることで、顧客満足度を高め、利益を高めることにもつながります。
返品率は利益に直結する重要指標と心得よう
たとえば、返品の影響範囲には次のようなものがあります。
コスト増加
返品処理には人件費や再梱包・再検品・再出荷・返金手数料などが発生します。商品が再販できない場合は在庫ロスや廃棄コストにも直結します。
業務効率の低下
返品対応は通常業務を圧迫し、スタッフの負担増になります。特に繁忙期は出荷遅延や顧客対応の質低下を招くこともあり、悩ましい問題です。
顧客満足度とブランドイメージの低下
スムーズに返品対応ができない場合、クレームの発生やリピート率低下につながります。一方で、柔軟な返品対応は信頼獲得とLTV(顧客生涯価値)向上に寄与します。
利益率への直接的影響
売上が立っても返品されれば、売上取消とコスト発生で大打撃。返品率が高いと利益率が圧迫されることになります。
返品は確かにEC運営における大きな課題ですが、仕組みや対応次第で、顧客満足度を高めながら利益率も改善できるチャンスに変えることができます。
次のセクションの業種ごとの返品傾向などを踏まえたうえで、より具体的な対策や工夫について見ていきましょう。
返品率とは?求め方と捉え方
返品状況を知るために「返品率」は意識しておくべき数値です。以下の式で計算できます。
※キャンセルや未発送分は「出荷数」に含めないのが一般的です。
この数値を単に減らすかどうかではなく、返品ポリシーの設計そのものが、顧客の購買行動や企業の収益構造につながります。たとえば返品ポリシーが厳しい場合、特に初回購入者や高単価商品では購入が慎重になりがちです。一方、柔軟な返品対応で「合わなかったら返品できる」という安心感があれば、購入の後押しになります。
つまり、返品を単なる損失ではなく「顧客体験を向上させる機会」と捉えて、バランスを見ながら「返品しやすさ」と「利益確保」の両面から考えることが、最終的にはお店の利益アップにつながるというわけです。
業種や商品カテゴリによって大きく異なる返品率
とはいえ、返品率は気になるもの。まず知っておくべきは返品率の”相場”です。業種や商品カテゴリによって大きく差があるので、自社製品のカテゴリでの平均返品率を把握し、返品が事業にもたらす”本当の影響”を考えながら対策を講じましょう。
返品率が高い業種では、返品を前提とした利益設計や返品データの活用による改善などが必要になることもあります。
それぞれの業種・商品カテゴリの一般的な返品率は次のとおりです。
返品されやすい商品カテゴリ
サイズや色の選択が必要で、使用感やフィット感が重要なものが多いためと考えられます。他にも、写真と実物の差が出やすい、感覚的な満足度(香り・音・触感など)が影響するなどの傾向もあります。
| 商品カテゴリ | 平均返品率 | 返品理由 |
|---|---|---|
| アパレル | 20〜40% | 色味・素材感のミスマッチ。試着できないため、サイズの理由も多い |
| 靴・スニーカー | 10〜15% | 足の形やサイズ感が合わない。特に初回購入時に返品が多い傾向あり |
| アクセサリー | 10~30% | 写真と実物の質感・サイズ感のギャップ。特に高価格帯で慎重になる傾向 |
| インテリア雑貨 | 5〜10% | 色味・サイズ・素材の印象違い。設置後に「思ったより大きい/小さい」など |
返品されにくい商品カテゴリ
「使用前に品質や仕様が明確にわかるもの」や「消耗・消費型の商品」などが該当します。スペックや仕様が明確で、使用前に品質が判断でき、感覚的な満足度に影響されにくいという特徴があります。また、衛生上・安全面・著作権などの理由で返品不可としているものもあります。
| 商品カテゴリ | 平均返品率 | 返品理由 |
|---|---|---|
| 書籍・雑誌・CD/DVD | 1〜3% | 内容が事前に明確で、購入後に返品する動機が少ない |
| 消耗品(洗剤・日用品) | 1〜3% | 使用前提で購入されるため、未使用での返品がほぼない |
| 食品・飲料 | 1〜3% | 衛生面の観点から返品不可が一般的。破損や誤配送以外では返品されにくい |
| 工具・文具 | 1〜3% | サイズや色の誤差が少なく、感覚的なギャップが起きにくい |
越境ECは返品率が高い!?返品リスクとチャンス
越境ECにおける返品は、まったく異なるルールと文化が絡んでいます。たとえば、米国では「返品は当然」の文化で、理由不要で返品可が一般的です。多くのECサイトで1〜2ヶ月ほどは返品を受け付けます。欧州では、通信販売において未使用品であれば購入後14日間は返品できる権利が消費者に保障されています。中国では「返品より交換」で対応する事業者が多いようですが、返品権も法的には整備されています。
返品ポリシーの策定のところで詳しく紹介しますが、海外と比べると日本は返品しにくい環境にあるといえるでしょう。しかし、それに慣れていると、越境ECでは返品の多さに戸惑うだけでなく、大きな痛手を負う可能性もあります。そこで、たとえば、次のようなことを意識して慎重に返品の戦略設計を行う必要があります。
返品時の関税・輸出入税の基本的な考え方
返品時には、「再輸入」または「再輸出」扱いになるため、以下のような税金・手続きが関係してきます。
- 関税の返還(還付):国によっては返品時に関税の還付申請が可能です(例:EU、アメリカ)。
- 再課税のリスク:再輸入扱いになると、再度関税が課されることもあります。
- VAT(付加価値税):EUなどではVATの還付申請が必要。条件を満たさないと返金されません。
- 通関手数料:返品時にも通関処理が必要となり、手数料が発生する場合があります。
- 返品理由の証明:「未使用」「不良品」などの証明が必要な国もあります(例:中国)。
返品時の送料や関税の負担
販売者の「返品ポリシー」や配送条件(インコタームズ)によって異なるため、誰がどう負担するかをあらかじめ記載しておかないと、大きなトラブルになりかねません。
方針としては、販売者が関税・送料をすべて負担し、返品時も販売者が再度負担する「DDP(Delivered Duty Paid)」と、購入者が関税を負担し、返品時も購入者が送料・関税を負担する「DAP(Delivered at Place)」の2つがあります。
返品ラベルと関税処理
返品ラベルの発行は、アメリカ・EUでは自動発行ツール(例:AfterShip、Return Helper)が主流になっています。関税返還については、米国では未使用・未開封の際のみ税関(CBP)に申請して許諾され、EUでは可能ですが、VAT還付にはIOSS番号や返品証明などが必要になります。
中国については返品商品が再販可能かどうかで、関税返還の可否が変わり、なかなか手続きが煩雑です。越境ECにおいて返品時の関税トラブルを防ぐには、次のような点を意識する必要があります。
- 返品ポリシーに関税・送料の扱いを明記
- DDPかDAPの配送条件を明確にする
- 返品ラベルと関税処理のフローを整備
- 返品理由・状態の記録を残す
- 現地関税のルールや文化を事前に調査
本稿では国内における返品ポリシーについて紹介しますが、ポリシー策定の考え方やポイントは越境ECと共通するものがあります。とはいえ、複雑な部分もあるため、各国に精通した事業者のサポートを受けることがおすすめです。
返品ポリシーで押さえるべき7つのポイント
それでは、日本における返品ポリシーの策定ポイントについて紹介しましょう。前述したような海外のECルール・文化に比べると、日本では返品しにくい・されにくい状況にあります。
日本では消費者に法的に保障された返品権(クーリングオフ)があるものの、訪問販売や電話勧誘など「強引な販売」が対象で、すべてに適用されるわけではありません。ECサイトなどの通信販売は原則対象外で、期間も8日間と短めです。
しかし、法令がないからと返品を厳しく制限すると、マイナスの影響が大きくなる可能性があるため、柔軟に対応する方がよいといえるでしょう。とはいえ、大きなトラブルにならないよう予め「返品ポリシー」を策定し、顧客に対して明確に示しておくことが大切です。
返品ポリシーの策定においては、次の7つのポイントを意識し、フローチャートなどで条件分けして決めておくと漏れもなく、効率的に判断ができるでしょう。アップデートも随時行いましょう。
① 返品・交換の条件
条件は業種・商品ごとに最適化する必要があります。具体的には次のような事項を記載します。
- 商品到着から〇日以内(例:7日以内・14日以内など)
- 未使用・未開封であること(タグや付属品の欠損がない状態)
- 特定商品(下着・食品・セール品など)を対象外とする
※「初回だけサイズ交換や返品可能」や、「1ヶ月間返品送料無料」など期間限定で条件を変える方法も有効です。
② 返品理由による処理の区分
返品理由は次のよう項目で分類し、具体的な内容を明記しておくことが大切です。
| 分類 | 具体的な例 |
|---|---|
| 購入者都合 | サイズ違い/色味が想定と異なる/イメージ違い/注文ミスなど |
| 店舗・配送ミス | 誤配送/商品違い/数量不足/欠品対応など |
| 商品不良・破損 | 初期不良/輸送中の破損/パーツの欠損など |
③ 送料・手数料の負担区分
送料・手数料をどちらがどのように負担するか、明確にしておくようにしましょう。
| 分類 | 対応例 |
|---|---|
| 購入者都合 | 購入者が返送料/返金手数料を負担するケースが多い |
| 店舗都合・商品不良 | 店舗が全額負担(着払いなど)で対応することが基本 |
※返品理由によって、返送料や対応フローなどが変わることを記載しておきましょう。
④ 返送・再送の手続き方法
顧客からの返送連絡や手続きについての方法を全て抽出し、詳細を記載します。例えば下記のような事項です。
- 返品申請フォームやマイページからのリクエスト受付
- サポート経由での個別対応(メールやチャット)
- 返品ラベルの自動発行対応(ツール連携も含む)
- 追跡番号付き返送の指定や返送期限の明記
Shopifyではこうした返品連絡・手続きについてアプリ(AfterShipやRecustomerなど)の導入で効率化できます。
⑤ 返金方法・タイミング
いつどのような形で返金されるのかを記載します。
- 返金方法:クレジットカード/コンビニ払い/銀行振込など、購入方法に準拠
- 返金タイミング:商品到着確認後⚪︎営業日以内(例:5営業日以内)。クレジット決済の場合はカード会社のサイクルによる。
※「返送確認後に返金」と明記することで未返送リスクを回避できます。
⑥ 交換対応の可否と条件
基本は「在庫がある場合のみ交換可」「サイズ違いの交換1回のみ無料」などと具体的に記載しておくと安全です。また再送の送料は初回無料または購入者負担というように、明確に記載しておきましょう。
Shopifyでは在庫連携システムと連動させることで、交換処理の自動化が可能です。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
⑦明文化と訪問者への見せ方
返品ポリシーとして公式ページ内に明記するだけでなく、商品ページにも「返品についてはこちら」のリンク設置を必ず行いましょう。また、チェックアウト時の確認・注文メールにも記載すると安心感が高まります。なお、表現は法律用語ではなく、ユーザー目線のやさしい言葉を使うようにしましょう。
Shopifyでは、チェックアウトページのカスタマイズが可能です。Shopify Platinumパートナーが提供する「BiNDec|チェックアウトカスタマイズ」アプリもおすすめ。詳しくはこちらのページをご覧ください。
基本的な返品ポリシー以外で注意するべき4つのポイント
様々な購入形態がある場合、返品ポリシーについても例外が生じます。基本的な返品ポリシーだけではフォローできない部分についてもしっかり準備しておきましょう。
① ブラックリスト登録ルール(頻繁な返品ユーザーへの制限など)の設定と運用
悪質な返品常習者や未払い顧客による損失を防ぐため、特定のルールを設定してブラックリストを作成し、購入の制限や確認などを行います。なおShopifyでは次のような方法で、ブラックリストの運用を効率化することができます。
- 公式アプリ「Shopify Flow」で自動化:プライバシーポリシーに記載したブラックリスト条件を設定しておくと、該当する人にタグを自動付与し、注文をブロックできます。
- 公式アプリ「Fraud Filter」:特定条件(例:過去に未払があったメールアドレスなど)に合致した注文を自動キャンセルまたは警告表示できます。「要対応顧客」として受注を保留・確認制にする設定も可能。
- 公式アプリ「RuffRuff」:ブラックリストタグが付いた顧客に対して商品購入を制限します。
トラブルを防ぐため、ブラックリスト条件(例:過去6ヶ月で3回以上の返品など)の明文化は必須となります。また、限定品や人気商品などについては、転売・不正対策としてさらに厳しい購入制限・再購入制限ルールを設けておくのもよいでしょう。
ただし、ブラックリスト自体は個人情報保護法に配慮し、外部共有は避けるのが鉄則です。もちろん、情報漏洩などにも留意し、誤って良質な顧客をブロックしないよう、記録と確認を徹底します。
② ギフト注文・代理購入についての返品ポリシー
ギフト注文や代理購入における返品ポリシーでは、通常の購入とは異なるトラブルや誤解が起きやすいため、別途での配慮が必要です。たとえば、次のようなことに考慮するとよいでしょう。
返品申請者
返品申請は購入者のみか、受取人もできるのか。受取人が返品を希望する場合は、どのような情報(注文番号や購入者の情報など)が必要か。
返金先の指定
返金はどのような方法で行なうか。購入者の支払い方法(例:クレジットカード、銀行振込)が原則で、受取人への返金は不可とするのが一般的です。クーポンやギフトカードでの返金を選択肢にするケースもあります。
返品理由と条件
受取人都合(サイズなど)での返品・交換が想定される場合、未使用・未開封・タグ付きなどの条件を厳格に設定しておくと安心です。
返品送料・手数料の扱い
購入者・受取人とも、返品にかかる送料は自己負担が一般的です。
ギフト包装・特典の扱い
ギフトラッピングやノベルティがある場合は、返品時に同梱が必要かどうかを明記しましょう。「ギフト包装代は返金対象外」などの記載も必須です。
個人情報の取り扱い
購入者からの返品申請時の返金や返品連絡などは購入者にのみ通知します。逆に受取人からの返品申請を受ける場合は、購入者に開示しないよう配慮しましょう。
Shopifyでは、ポリシーの設計・明文化に加え、通知・明細書のカスタマイズが柔軟にできるので、きめ細やかに対応することができます。たとえば、通知メールではLiquid変数を使って、購入者と受取人が異なる場合の文言を条件分岐で作成・表示できます。
またShopify標準では金額非表示の納品書は自動生成されませんが、「BiNDec|帳票出力」などのアプリを使ってテンプレートを編集すれば、ギフト注文時は「金額記載なし」「返品方法の案内あり」の納品書を出力できます。
「BiNDec|帳票出力」について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
③ 予約商品・受注生産品の返品ポリシー
予約商品や受注生産品については、顧客との信頼関係を保ちつつも、EC事業者としての損失リスクを最小限に抑えることを意識する必要があります。特に受注生産品は、他の顧客に販売ができないため基本的にキャンセル不可・返品不可とされます。予約商品についても、オーダーメイドや季節性商品など再販が困難な商品はキャンセル不可・返品不可としてもよいでしょう。
商品ページに明確に記しておき、チェックボックスや注文確認画面で「同意を得たこと」を残せるようにしておくと確実です。注文完了メールにもキャンセル条件を再掲しておきましょう。
ただし、「キャンセル不可」としていても消費者契約法 第9条1号で平均的損害額を超える違約金は無効とされます。いざトラブルになりそうなとき、キャンセル料の根拠として示せるよう、原材料費や製造コスト、再販不可性などを整理して明文化しておくと安心です。
Shopifyでは、ポリシーの設計・明文化に加え、商品タグや商品タイプに「予約」「受注生産」などを設定すると返品ルールとの連動ができます。キャンセル期限付き(例:発送7日前まで)などの段階的なルールも設定でき、また帳票出力アプリを使ってテンプレートを編集すれば、「受注生産品につき返品不可」の文言を明細書にも自動挿入できます。
こちらの記事も併せてご覧ください。
④ 返品に伴うポイント・クーポン処理
返品による返金はなかなか痛いもの。その際に、等価でのポイントやクーポンなどで対応すると、会計面や作業面での影響を抑え、リピーターの獲得や顧客満足度アップにもつながります。ただしメリットだけでなくデメリットもあるので、返品時のポイント変換やクーポンの再発行のルールを明文化するなど、慎重な運用を意識しましょう。
メリット
- 顧客満足度の維持:ポイント返還でも顧客が「損をした」と感じにくくなる。
- 再購入を促進:返還されたポイントや再発行されたクーポンが、次回購入の動機になる。
- 現金流出の抑制:ポイント返還により、キャッシュアウトを回避できる。(特に返品が多い業種で有効)
- LTV(顧客生涯価値)の向上:ポイント再利用でリピート率や平均購入額が上がる可能性がある。
- 不正防止:現金化できないことで悪用リスクを抑制できる。
デメリット
- ポイント残高の調整やクーポンの再発行処理が煩雑になりやすい。
- クーポンやポイントの反映について問い合わせが増える可能性がある。
- 同じ返品でも「現金返金の人」と「ポイント返還の人」が混在すると不満が出やすい。
- 有効期限や再利用条件の管理が必要で、有効期限への不満が出ることもある。
Shopifyでは標準機能では返品時に使用済みのクーポンの再発行はできません。そこで、管理画面で新しいディスカウントコードを手動で発行し、顧客にメールで通知するという方法を取ります。
もし自動化したい場合は、アプリなどを使えば、返品理由に応じてクーポンの再発行ができます。
また、Shopifyでのポイント付与については、アプリの導入が必要です。「BiNDec|ポイント」は特定の顧客に対して、管理画面からポイントの増減調整が可能です。詳しくはこちらのページをご覧ください。
⑤ サブスクリプション商品の中途解約・返金規定
サブスクリプション商品の中途解約・返金規定は、通常の商品販売とは異なる設計が必要です。まずは解約・返金の可否と条件を明確に示しましょう。ポイントは次のとおりです。
- 途中解約の可否:「いつでも解約可能」「次回請求日の〇日前まで」など
- 返金の可否:「日割り返金なし」「未発送分のみ返金」など
- 返金対象の範囲:「未使用分のみ」「発送済みは対象外」など
- 無料トライアル中の解約:「無料期間中の解約で請求なし」など
ただし、あくまでEC事業者側からの条件提示なので、顧客の同意を得て、納得してもらう必要があります。商品ページへの「キャンセル・返品不可」の明記の他、FAQページやチェックアウト時の同意チェックボックス設置、注文確認メールへの記載などを行っておくと安心です。
Shopifyでサブスクリプション商品を取り扱っている場合、導入しているアプリを通して解約のタイミング・返金条件・通知設定などを柔軟にカスタマイズできます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
Shopifyにおける基本的な返品フローと対応設定
それでは具体的に、Shopifyでの基本的な返品フローと対応設定について、ステップごとに紹介します。
事前に行っておくべき返品設定
EC事業を開始する前に返品ルールは詳細まで決定し、Shopifyでの設定もしっかり行っておきましょう。

①返品ルールの設定
Shopify管理画面の「設定」→「ポリシー」→「返品ルール」 から、返品期間、返品送料、返品手数料などが設定できます。返品不可の商品やコレクションも指定でき、返品対象外の商品には返品リクエストができなくなります。
②返品ポリシーの明文化
Shopify管理画面の 「設定」→「ポリシー」→「返品と返金のポリシー」から設定できます。HTML形式で記述し、リンクや太字も入れられます。この設定でチェックアウト画面のフッターに自動的に返品ポリシーが表示されます。
③「セルフサービス返品」の有効化
「設定」→「お客様アカウント」→「セルフサービス返品を有効化」を行うと、顧客がマイページから返品リクエストを実施することができます。
④返品ラベルの準備
米国では自動生成できるようになっていますが、日本国内や越境ECでは対応していません。
アプリの活用や、既存の配送業者(ヤマト・佐川など)で作成したラベルをPDFやJPEGでアップロードしたり、URLで共有したりして対応します。
⑤通知メールのカスタマイズ
「設定」→「通知」→「お客様への通知」や「スタッフ通知」で、「返品受付通知」「返金通知」「注文キャンセル通知」などのメールテンプレートを編集できます。返品条件や返金タイミングなどを明記すると、顧客に安心感を与えます。
顧客側の返品フロー
顧客側から返品作業がどのように見えるか、テストをしておくことが大切です。「セルフサービス返品」を利用するかどうかの決定に加え、顧客側のステップについて不具合がないか、確認しておきましょう。
セルフサービス返品を利用する場合
- マイアカウントにログイン(「新しい顧客アカウント」機能が有効となっている場合に利用可能)。
- 注文履歴から返品したい注文を選択し、選択式で返品理由を入力して、返品リクエストを送信します。
- ECサイト側に通知が届き、承認されると返品ラベルや返送先情報が表示されます。
- 指定されたラベルを使って返品分を発送、または自費で返送します。
- 返品完了後、返金または交換処理が行われます。返品ステータスは随時マイページで確認できます。
セルフサービス返品を有効にしていない場合は、顧客側から「お問い合わせ」や「返品フォーム」「チャット」などから連絡をもらい、発送先や返品条件の案内のやりとりの後、返送となります。
ECサイト側が商品を確認してから返金・交換となり、それまでの返品状況の確認はメールなどでの人力で対応することになります。煩雑な作業になることが多いため、一定の返品が予想される場合は、セルフサービス返品を利用することをおすすめします。
EC事業者側の返品処理フロー
返品処理のフローについては、詳細なマニュアルを作成しておくようにしましょう。たとえば、具体的な作業としては下記のようなものがあります。
- 返品の通知を受けたら返品ラベルや返送先情報を顧客側に送付します。返品ラベルはアプリなどを利用し、既存の配送業者(ヤマト・佐川など)で作成したものを活用すると便利。
- 顧客から返送があったら、倉庫や店舗で状態確認・検品を行います。再販可否の判断と在庫補充の有無を決定します。
- 返品受取や返金通知の連絡を行います。予めカスタマイズしたものを用意しておくと効率的です。
- 管理画面から「返金」ボタンをクリックすると、元の決済方法(クレジットカードやPaypalなど)に返金されます。ポイントやクーポンの対応は手動またはアプリなどでの自動化も可能です。
返品・返金後の処理
返品を受け、返金処理を行った後は、在庫・会計・顧客対応・分析の4つの観点で対応が必要です。
在庫管理
- 在庫の補充:返送された商品が再販可能なら、「在庫に戻す」にチェックを入れて補充します
- 不良品の除外:再販不可な場合は「在庫に戻さない」を選択して、廃棄・検品記録を残します。
- 返品率の記録:商品ごとの返品傾向を把握し、商品改善や説明文の見直しに活用します。
会計・売上処理の調整
- 売上のマイナス計上:返金分は売上から差し引き、連携させている会計ソフトと整合を取りましょう。
- 決済手数料の確認:Shopify Paymentsでは返金しても手数料は戻らないため、利益率に注意しましょう。
- 返金理由の記録:会計監査や内部統制の観点から、返金理由を明記しておくと安心です。
顧客対応・通知の完了
- 返金通知・返品完了の連絡:Shopifyの通知テンプレートで自動送信されますが、「返金完了しました」「ご不便をおかけしました」などの一言を添えるなど、文面のカスタマイズと信頼感がアップします。
分析・改善への活用
- 返品理由の集計:「サイズ違い」「イメージ違い」「破損」などを分類し、商品改善やFAQ整備に活用します。
- 返品率のモニタリング:商品別・顧客別・キャンペーン別などで分析し、返品リスクの高い要因を特定します。
- 返品対応時間の記録:業務効率化やスタッフ教育の指標として活用するとよいでしょう。
返品コストを削減し、ECの利益率と顧客満足度を向上
返品コストを削減しつつ、利益率と顧客満足度を両立させるには、「返品を減らす」だけでなく、「返品体験を最適化する」視点が重要です。実務的かつ戦略的な観点から、意識すべきポイントや実例を紹介します。
信頼を生むポリシー設計と返品対応キャンペーン
ポリシーは厳しければよいというものではなく、返品できる安心感は購入の後押しにもなります。レビューやFAQを充実させることや、期間やアイテムを決めて、自宅試着便や返品無料キャンペーンなどを戦略的に活用するのもよいでしょう。
海外のファストファッションブランドの多くは、柔軟な返品ポリシーに加え、返品無料キャンペーン、ストアクレジットやクーポンの提供などで売り上げをあげてきました。特にZ世代などの若年層に効果的だと言われています。
購入前の不安解消|チャットツールで24時間接客&返品抑止
例えば、色味やテクスチャーなど情報が限られるコスメ系ECでは、「肌に合うかな?」「思った色と違ったらどうしよう…」といった懸念を抱えたまま購入に至り、その後「イメージ違いによる返品」につながるケースがあります。
こうした購入検討者の疑問を解消する手段として、Web接客ツールを導入すれば、24時間いつでも顧客の質問に自動で応答できます。
さらに、AIチャットボットと有人対応を組み合わせられるサービスであれば、複雑な相談が発生した場合もスタッフがシームレスに対応を引き継げるため、実店舗さながらのきめ細やかなサポートが可能です。顧客は安心して納得の上で購入できるため、購入者都合による返品を抑制できる効果が期待できます。万が一返品が発生した場合でも、チャットを通じてスムーズに案内でき、顧客体験を損なわずに対応できます。
コスメECサイトがチャットツールによる24時間自動応答体制を構築。購入前の疑問解消によって返品リスクを低減しつつ、月100件超のキャンセル処理もAIで自動化。顧客満足と業務効率の両立を実現しました。
このようなWeb接客をShopifyで実現できるツールに「チャネルトーク」があります。大手コスメECにも導入されており、上記のような施策を実現可能です。
「購入前の不安を解消する仕組み」を整えることは、返品抑止だけでなく、ブランド価値の向上や顧客ロイヤルティの醸成にもつながります。

これらのWeb接客の仕組みを含め、業種・業態にマッチしたShopify連携やシナリオ設計まで、Shopify PlatinumパートナーのBiNDecではトータルにご支援可能です。チャネルトークの導入サポートや、他のShopifyアプリとの組み合わせによる最適な運用設計を通じて、返品の未然防止から効率的な対応設計まで、一貫してEC事業の成長を支えます。
チャネルトークについては、こちらの記事でも紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。
商品説明の充実・正確化
詳細なサイズガイドや素材説明、使用感の記載など購入後をリアルに想像できるような情報を提供しましょう。テキストだけでなく、高品質な写真や使い方などの動画、360度ビューなどの活用も有効です。
返品の多いアパレル系などではモデルの身長・着用サイズを明記し、体型の異なる着用例などを掲載するとよいでしょう。
いわゆるモデル体型のモデルではなく、普通体型などのリアルな着用者の写真を掲載。具体的なイメージが持てるようになり、返品率を下げることに成功。
商品・物流面での工夫
返品後に再販できない衛生商品などには開封シールなどを導入したり、商品間違いや破損品の出荷を未然に防ぐためにWチェック体制や写真記録付き検品などを行ったり、商品や発送・物流面での工夫で返品率を下げます。
Shopifyによる返品フローの効率化、返品後のバックヤード効率化、チャットボット対応で返品前の問い合わせ削減など、工夫できることは多くあります。
返品マニュアルの作成は返品フローを見直す上で有効。全社で取り組むことで返品業務を効率化・正確化することで、業務負担を減らし、顧客の信頼を高めることに。
バックエンド業務の効率化については、こちらの資料でも解説しています。ぜひ併せてご覧ください。
返品対応はスピードと共感がカギに
返品対応は迅速かつ正確性が重要ですが、同時に「共感」も大切です。「返品=商品への満足度が低い」ということを意識し、顧客の残念な気持ちへの共感があればブランドへのロイヤリティ低下を防ぐこともできるでしょう。不備があった場合のお詫びや返送料負担分として、クーポンやポイントで還元するなど、次回購入を促す施策も効果的に活用しましょう。
初回返品者限定で次回割引クーポンを提供し、2回目の購入を促進。柔軟な対応に顧客満足度が高まり、リピーターとなる人が増えた。
返品を環境価値から捉える
「返品=悪」ではなく、選択肢の一つとして扱いながらも、「返品しないことが環境にやさしい」という意味づけを提案することで、顧客の共感とブランドの信頼を高めることができます。たとえば、近年のサステナビリティへの共感として、簡易包装や配送費負担などへの協力を得ることがができるでしょう。
返品送料の一部を環境団体への寄付や植林活動に充てるなど、ポジティブな循環を提示することで、返送料負担に納得感を与えられた。
返品理由の分析と返品ポリシーの見直し
返品対応において最も重要なのは「分析と見直し」ではないでしょうか。返品対応は単なる“処理”ではなく、売上や利益、顧客満足、ブランド価値を左右する重要なデータの収集機会であり、改善のチャンスです。商品や提供情報の改善、不良率・品質管理の評価、マーケティング施策などに活かせます。当然、返品ポリシーの見直しも忘れずに実施しましょう。
「LTVが高い顧客ほど返品率は低い」との傾向を把握したことで、LTVの高い顧客にのみ「試着購入キャンペーン」のクーポン配布や「いつでも返品送料無料」などの特典を提供。リスクを抑えつつ、VIP待遇感を出し、ロイヤリティを高めることに成功した。
Shopifyアプリでもっと効率的&効果的に返品対応ができる
返品対応を戦略的に設計するのは大変ながら、作業部分はできるだけShopifyを活用して効率化したいもの。
文中にも登場していましたが、Shopifyには16,000を超えるアプリがあり、さまざまな機能を自社の求める内容に合わせて導入でき、様々な施策を効率的かつ効果的に実施することができます。
| アプリ名 | 日本語対応 | 特徴 | 費用 |
|---|---|---|---|
| AfterShip Returns Center | × | 多言語対応で越境ECにも強い。返品ポータルとして、自動返品承認・クレジット、QRコード返品・返品分析機能などを提供。 | 月3件までは無料(基本的な返品受付・通知のみ)。月額料金で、件数と機能で11ドル〜239ドルのプランあり。 |
| Return Helper | ◯ | 越境ECに特化し、20カ国以上の現地倉庫を持つ。再梱包や再出荷対応を実施し、再販へと転換できる仕組みを提供。オプションで写真撮影やリパッケージ、返送、破棄などにも対応。 | 初期費用はデポジット制+従量課金制(件数ベース)返品1件あたり 約3.85ドル(入庫+保管+出庫) |
| Recustomer | ◯ | 返品・交換・キャンセルの自動化、返品理由の収集・分析、自宅で試着、自動集荷・配送連携、倉庫管理・顧客ツールとの連携も可能。 | 要見積 |
| Fraud Filter | × | ブラックリスト登録で、自動キャンセルや警告表示など。Shopifyの「不正リスク判定(低・中・高)」と組み合わせて活用可能 | 無料(Shopify公式アプリ) |
Shopifyで戦略的に返品対応を設計するならBiNDecにお任せ
返品は避けられない課題ですが、仕組み次第で顧客満足度や利益率を高めるチャンスにも変えられます。ここまで解説した通り、Shopifyなら、返品ポリシーの明文化やフローの自動化、データ活用までを一元的に整備することが可能です。
さらに、BiNDecでは、チャネルトークをはじめとするWeb接客や、ポイント施策・チェックアウトカスタマイズなどを組み合わせた「BiNDec MODEL」をご提供。
「返品を未然に防ぐ仕組み」から「発生した返品の効率的な処理」まで、業種や商材に合わせてShopifyでの最適な運用設計をトータルにご支援します。
返品対応の改善は単なるコスト削減ではなく、顧客体験を向上させ、ブランド価値や売上成長へとつなげる施策です。EC基盤の見直しやリプレースをお考えの方は、ぜひBiNDecにご相談ください。
\返品課題を解決し、売上成長を実現/