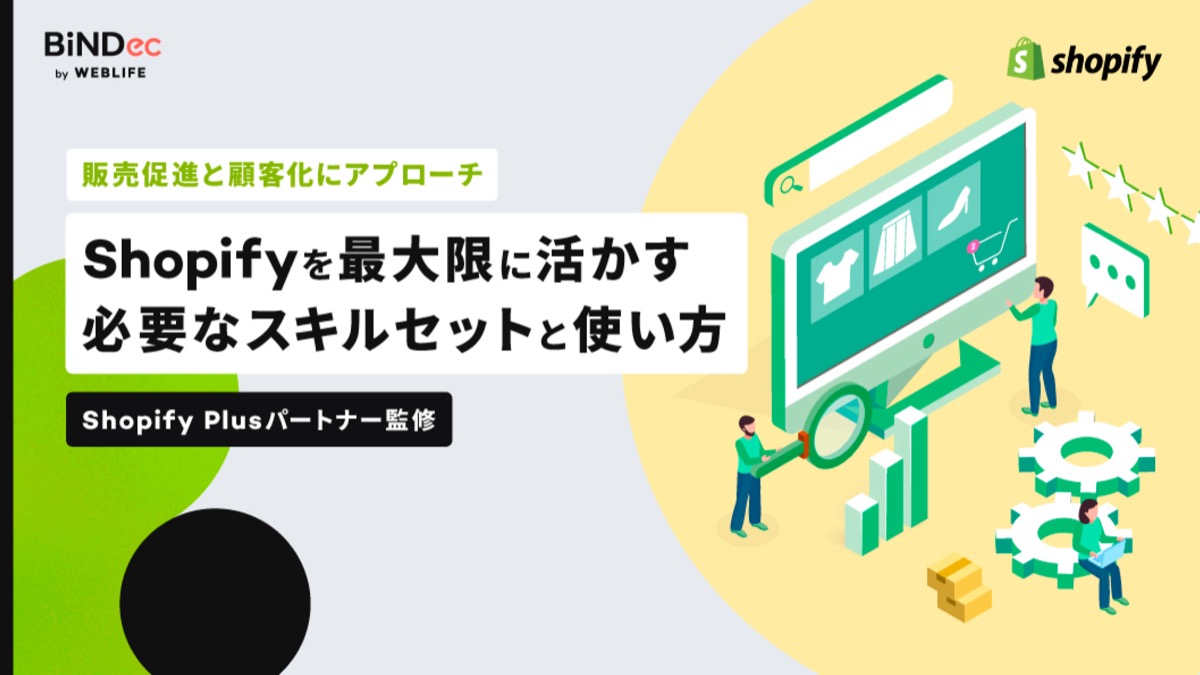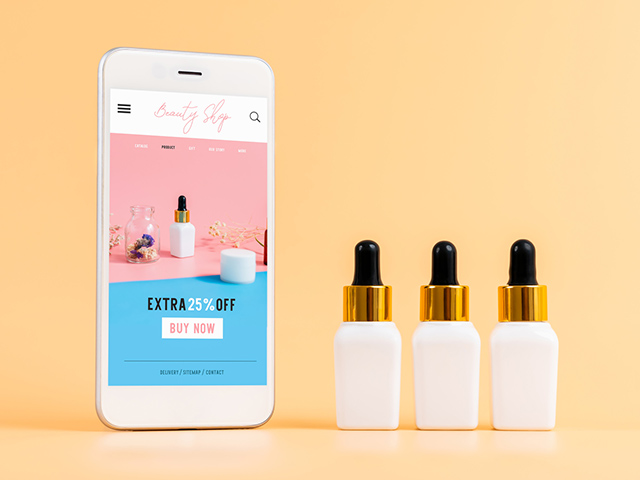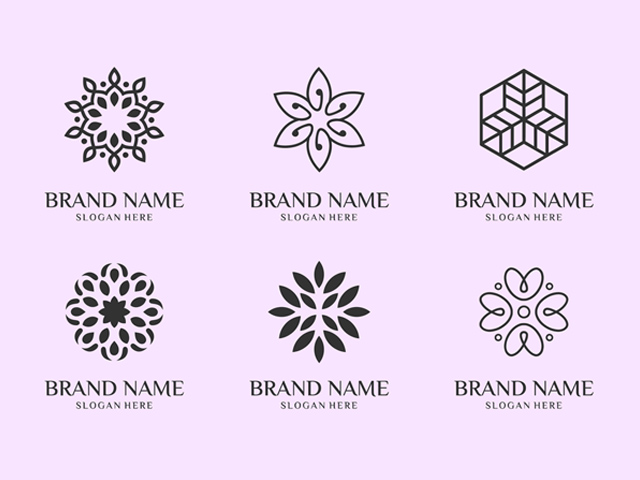D2Cは当初、新進のスタートアップ企業による新しいビジネスモデルとして捉えられていましたが、現在では、多くの企業が取り入れ始めており、自社の顧客とコミットするための接点へと変化しつつあります。
今回は、D2Cに欠かせないECサイトを運営するためのプラットフォーム選びについて成功例も交えながら解説します。
→D2CのECサイト構築もおまかせ。BiNDecがオンラインにてご相談を承ります。
D2Cに適したプラットフォームとは?

D2C(ディー・ツー・シー)とは「Direct to Consumer」の略で、一般に、メーカーや企業が、卸や小売店、ディーラーを経由せずに消費者(Consumer)へ直接商品を販売するビジネスモデルです。
そんな直接販売をするために欠かせないのが、自社独自の販売拠点です。D2Cの場合、その拠点はまずはウェブ経由となるため、ECサイトが欠かせません。しかし、新規にD2Cを始めようと考えるメーカー(製造業者)、ブランドなど、これまでは販売に特化した自社のウェブチャンネルを持っていないケースも多いかと思います。また持っていても、商品点数が少なく本格的な販売には向いていないこともあります。
では、どのようにしてD2Cに向いたECサイトを構築・運営するのがよいのでしょうか。
D2C成功へのコツを紹介。こちらの記事もあわせてご覧ください。
→D2CのECサイト構築もおまかせ。BiNDecがオンラインにてご相談を承ります。
ECサイトの構築には3つの方法がある
ECサイトの構築方法には、大きく分け「開発型」「半開発型」「SaaS型」があります。
フルオーダーの開発型ECサイト
開発型は、スクラッチ開発・オーダーメードなどとも言えるもので、要件を作成して、サイトのデザイン、遷移、機能など、すべてをデザイン開発・プログラミング開発して構築する方法です。
開発型のメリットは、何から何までオーダーメイドとなるので、内容と費用次第で他社にはないデザインや機能を作りたいという希望が実現しやすい点があります。
一方で、要件定義、仕様設計、画面設計、デザイン制作、そしてプログラミング開発などに関して、すべて提案をお願いし、その内容を確認して構築・テストしていくには開発費も期間もかかりますし、担当者にもそれなりの知見が求められます。
また、改良やバージョンアップを行う場合も、追加開発のプロジェクトとなります。ウェブの世界は流行や新しいサービス誕生など潮流がすぐに入れ替わるので、新規機能の追加などが重荷になる可能性も視野に入れておきましょう。
パッケージを改変する半開発型ECサイト
パッケージソフトと呼ばれるECに特化したサイトが構築できるプログラムを用いて、そのプログラムを一部改変して構築する方法です。
自社オリジナルのデザインを追加することで、汎用性の高い機能などは開発型よりもハードルは低く実装し、かつ自社だけのデザインや機能を加えることでオリジナリティも出すことができます。
半開発型のメリットはコスト面では低めに抑えながらも、自社独自のECを構築できることです。開発の際に、独自の機能を盛り込むことなどもできます。
一方デメリットは、パッケージ自体のバージョンにコントロールされる点です。自社で不要に思えても、バージョンアップが実施されれば更新とメンテナンス、仕様変更への対応なども検討しなければなりません。
ただし、コストを抑えようと保守契約を結ばないでサイトを放置してしまい、個人情報漏洩につながった事故も過去に多数起こっていますので、セキュリティ面でバージョンアップは必ずチェックすべきです。
サーバーいらずのSaaS型
SaaS(Software as a Service:ソフトウェア・アズ・ア・サービス)とは、クラウドにプログラム(ソフトウェア)を置き、ユーザーにはインターネット経由でプログラムを利用してもらえるサービスの総称です。サイト構築の機能自体が提供されているので、サイトのデザイン、決済機能、サイトの遷移などのようなものはすぐに利用できます。
SaaS型のECプラットフォームのメリットは、ほとんどの機能はすぐに使えるようになっており、商品情報やコンテンツの制作・登録などを行うだけでEC運用が始められることです。デザインのカスタマイズや追加機能ももちろん行えますが、SaaSのプログラムで許容される範囲となるので、独自開発なら可能でもSaaSでは追加できない機能もあり得る、というのはデメリットと言えるでしょう。許容範囲はサービスによりさまざまです。
効率やコスト重視ならSaaS型がおすすめ

ここまで、主なECサイトの構築方法を説明してきましたが、すばやくECの構築でき、コストパフォーマンスも高いのは、SaaS型のプラットフォームになります。
まず、SaaS型であれば自前のサーバーやソフトウェアなどを買いそろえる必要がありません、また保守もクラウドサービスのため、ハードを含めた自社サーバーなどでの保守に比べると割安感があり、大半はSaaS側で自動対応しています。そして、すぐに使い始められることもあって、開発型や半開発型に比べて起ち上げがスピーディに済みます。
D2Cで新規のチャレンジをする場合は特に、開発の時間や手間を抑え、低リスク、低コストでECサイトを始められるとあって、現在はSaaS型の人気が上がっています。もちろん、低コストであっても高いクオリティ、業績が上がるECサイトの構築が可能になっていることも人気の理由です。
ECのプラットフォームごとの代表的なサービスを紹介。こちらもあわせてご覧ください。
→D2CのECサイト構築もおまかせ。BiNDecがオンラインにてご相談を承ります。
D2Cに欠かせないECプラットフォームの特徴や選ぶポイント
SaaS型でEC構築環境を提供するサービスは、一般にECプラットフォームとも呼ばれます。このECプラットフォームにも多数のサービスがあり、どれを利用するのがよいのかと迷うことがあると思います。
そこで、ECプラットフォームを選ぶときのポイントについて以下にまとめました。
セキュリティの高さと堅牢性
D2Cプラットフォームは、クレジットカード情報や顧客の個人情報を取り扱うため、まず第一に信頼できる高いセキュリティが求められます。もちろん一般のウェブサイトでもセキュリティは大事ですが、ECでは情報を盗まれてしまうと、クレジットカードを不正利用されたり、顧客の情報やパスワードが別のサイトで使われるなど被害が大きくなります。もしも情報漏洩が起これば、企業の信用にも関わります。
セキュリティと並び、365日24時間、事故やサーバーを止めることなく安定して動くシステムの堅牢性も重要です。アクセス集中で動作しなくなったり、落ちてしまうようなサービスを使うのは担当者も顧客も不安ですよね。
セキュリティ面と安定した運用に信頼のおけるプラットフォームを選ぶことはビジネス上、必須と言えるでしょう。
EC担当者がチェックすべき脆弱性について、詳細はこちらをご覧ください。
スピードと拡張性
サイトのレスポンス速度も重要です。もし低価格に運用できるECサーバーやプラットフォームがあっても、その分レスポンスが悪いサイトになってしまうと、商品がすばやく表示できなかったり、決済画面が異様に遅くなるなど、購買意欲を低下させることに繋がります。こういったスピードについては、運用し始めてからの改善が難しいこともあるので、契約前によく調査しておく必要があります。
拡張性についても同様です。追加したい機能があったとして、それが可能か運用開始前に調べる必要があります。また、数年後に拡張が必要になった際にそれが行えるのか、またどのような開発で行えるのかなど、プラットフォームの特性を事前によく把握しておきましょう。
越境対応の有無
インターネット上では世界へ向けての発信が低コストに可能ですから、海外へ向けても商品を販売する「越境EC」を展開する企業が増えています。越境ECを行うためには多言語でのサイト運用ができることや、各国に対応したの配送料金や決済方法が用意できるか、事前に調べておく必要があります。
越境ECについての詳細はこちらの記事をご覧ください。
基幹システム連携、顧客情報の一元化が可能か
D2Cをスモールスタートするのであれば、自社内とのシステム連携が不要だと思われる企業担当者も多いかもしれませんが、エンタープライズ事業としてEC販売を展開しようというときに、社内のリソースと連携ができないECプラットフォームを使うすることはお薦めできません。
商品データがあればそのデータベース、顧客情報については顧客管理(CRM)システム、あるいは、社内の基幹システム(ERP)との連携を行えるような効率化が見込めるプラットフォームを選ぶべきです。
MAツールなど外部のマーケティングとの連携が可能か
D2Cでのマーケティングはウェブマーケティングがメインです。売上を上げていくためにもECプラットフォームは各種マーケティングツールとの連携が可能か事前に把握しておけると良いでしょう。
マーケティングツールが含まれているプラットフォームもありますし、それに加えて外部連携が豊富なものあります。ネット広告の出し方がどうなっているかなども確認しておきましょう。
→D2CのECサイト構築もおまかせ。BiNDecがオンラインにてご相談を承ります。
エンタープライズ向けD2Cでよく使われるECプラットフォーム紹介
ここまでに紹介したECプラットフォーム選びの特徴を踏まえつつ、現在よく選ばれている、エンタープライズ向けのSaaS型ECプラットフォームを紹介しましょう。
Shopify

Shopifyは、グローバル175か国で利用されているSaaS型ECプラットフォームです。2006年にカナダでスタートしたサービスですが、現在ではアメリカのECサイトの66.8%のシェアを獲得されるほどポピュラーな存在となっています。
Shopifyの特徴は、大規模ECにも耐えうるレスポンスの速いEC機能を、クラウドで低価格で提供、そして、販売に適したUIを豊富なテンプレートと共に提供することで、機動力のあるEC起ち上げを可能にすることです。時代の動きやビジネスのステップに合わせ、ECサイトを拡張していきたいD2Cの運用に向いており、アメリカではD2Cプラットフォームの代名詞となっています。
そのほかのメリットとしては次のようなことが上げられます。
メリット1:低コストで始められる
Shopifyは、低コストで利用できることで多くの支持を集めています。個人向けのベーシックプランで33ドル〜です。エンタープライズでお薦めのプランでも、月払いで399ドルとなっています。
メリット2:機能が豊富
ECプラットフォームの中に、ECバックオフィスやマーケティングのための多くの機能がすでに含まれています。これも多くの企業にShopify が選ばれる理由のひとつです。例えば以下のような機能があります。
- 在庫管理
- 顧客データの管理
- 配送料自動計算機能
- クレジットカードをはじめとする多才な決済
- カゴ落ちのリカバリー
- 検索エンジンの最適化
- 8,000以上の追加機能をアプリで提供
在庫管理についてはWMSとの連携が行えたり、顧客データなどは社内CRMとの連携も可能で、エンタープライズに欠かせない拡張性も用意されています。
メリット3:外部サービス連携ができる
Shopifyの商品は、Amazon、楽天などへの同時掲載が可能です。また、Instagram、Facebookなど、SNSとの連携にも対応しています。
現在では、商品をAmazonや楽天で商品を検索したり、SNSで検索する人も増えています。こういった顧客接点を最大限に活かし、手間をかけずに、より多くの顧客にアプローチできるシステムがShopifyには用意されています。
Shopifyのデメリットとしては、開発機能が非常に速く、年数回と新しい機能が次々投入されることもあって、それらを活かすにはShopifyに詳しい人材や、コンサルタントがいないと、提供された機能を使う機会を無駄にしてしまう可能性があることです。
また、カスタマイズの自由度があることにも注意が必要です。部分的にプログラムやテンプレートを変更することもできますが、公式サポートされていない機能追加をした際、バージョンアップの際に不具合が出ることがあります。運用方針についてもメンテナンスがしやすい方針を最初に立てておくことがポイントです。
Shopify(ショッピファイ)とは?費用、機能を全網羅で解説!こちらもあわせてご覧ください。
ecforce

ecforceは日本発のD2Cプラットフォームとして、D2Cの支援なども行う株式会社SUPER STUDIOが提供するEC基幹システムです。
フォーム一体型LPとも言われる、ランディングページの下にすぐに定期購入ができる購買促進ページを作成できることが、売上アップが可能なEC機能の一つとなっています。もちろん、他のECサイト同様、通常の商品ページも構築可能です。
メリット1:コンサルによる手厚いサポート
D2C支援に特化しているサービス会社のため、契約後に手厚いサポートが期待できます。どのようにツールを使っていくかのアドバイスを受けられるイメージです(ページ制作や決済の手配は、サービス利用者側で行います)。
メリット2:新機能が多くリリース
顧客の購買データをもとにしたパーソナライズ、アップセルやクロスセルの仕組みの提供、MAの提供など、さまざまなマーケティング機能を提供しています。月額料金に含まれるため、機能追加に購入予算は必要なく、使いたい機能を活用することができます。
メリット3:パートナー企業との協業が可能
ecforceは、利用者がページ制作や開発について相談できるように、ウェブ制作会社などに対してパートナープログラムを提供しています。信頼できるウェブ制作会社を介してecforceを利用すれば、用意された機能のメリットを存分に活かしてD2C運営での売上アップに取り組めると言えます。
デメリットとしては、LPページ以外の通常の商品ページなどのコンテンツのデザインテンプレートの選択肢が少なく、デザインについては別途で制作が必要です。なお、決済システムも別途契約が必要。
また、価格面では、他のサービスと比べ初期費用が148,000円と高めとなっているので、契約前に、自社が必要としている機能や支援なのかを見極める必要はあるでしょう。
makeshop

makeshopはGMOメイクショップ株式会社により運営されているASP型のサービスで、構築・運営・集客などECに必要な機能を多く有しています。
メリット1:オリジナルテンプレートがすべて無料
173種類のテンプレートが無料で利用できます。また、カスタマイズにはHTMLや、独自変数タグと呼ばれるmakeshop独自のタグを使用します。また、歴史があるサービスで機能数が非常に豊富と言われます。
メリット2:エンタープライズ版がある
makeshopは個人向け以外にエンタープライズ版が提供されています。初期費用11万円〜、登録商品数5万商品、20アカウントが発行され、月額60,500円で利用できます。エンタープライズはそのほかのプランと異なり、個別カスタマイズなどを受けることが多いと言えます。
メリット3:関連のコンサルティング会社がある
GMOのグループ力を活かしたマーケティングがサイト制作などを開設できる関連企業が多数あります。
デメリットとしては、機能が多すぎて慣れるまで操作が難しいといった意見も聞かれるようです。また、デフォルトではドメインのリダイレクトに対応していませんので移行の予定がある場合は、事前に対応について調べる必要があります。
カラーミーショップ

カラーミーショップは、GMOペパボ株式会社の提供する日本製のショッピングカートサービスで、2005年のリリース以降、14万店舗以上が運用してきました。定期販売フォームや決済付きLPなど、売上に貢献するサービスを多数取り揃えており、常にECに求められる機能追加も行われています。
メリット1:有名ブランドも利用
個人でも利用可能なサービス月額から提供されているカラーミーショップですが、有名ブランドにも採用されています。京都吉兆、銀座鈴屋、クリスピー・クリーム・ドーナツなどの実店舗をもつブランドが利用しています(2024年1月現在)。
メリット2:コストパフォーマンスに優れる
初期料金も月額料金も安く、スタートする際も長期に運用する場合もコストパフォーマンスに優れます。アプリによる機能拡張もあります。
また、テンプレートは無料と有料があり、カスタマイズがしやすく美しいデザインのサイトが作成できるため、ページ開発コストを抑えることが期待できます。
メリット3:SEOに強いCMS連携
コンテンツマネジメントシステムにはWordPressを無料で導入でき、ECと同じドメイン上で運用することで、SEOに強いサイトに育てられます。とくにCMSを使い慣れたWeb担当者などが運用する場合は、スキルを活かしてECを運用できます。
デメリットとしては、いわゆる容量無制限に利用できるSaaSとは違い、ホスティングサーバーのように利用できるディスク容量がプラン選択に影響する点です。コンテンツや商品が増えることで容量も必要となってくるため、契約プランには注意が必要です。ゆくゆくはもっと大規模な展開をしたいと考える場合は、慎重に検討すべきかもしれません。
→D2CのECサイト構築もおまかせ。BiNDecがオンラインにてご相談を承ります。
D2Cのプラットフォーム選びでよくある失敗とは?
プラットフォームを決断する時には、価格、コスト、機能面の使い勝手などが判断材料になるかと思います。しかし、導入時には見えていなかったことが、後になって問題になることも。そこで、D2Cで後悔することがよくあるプラットフォーム選び・サイト立ち上げについて解説します。
コスト重視で選んで拡張性やセキュリティ要件が満たなかった
D2Cの立ち上げ時は、月額保守費用が抑えられるプラットフォームに強く魅力を感じるかもしれません。
しかし、拡張性に欠けたサービスを選んでしまうと、次のステップへ成長する際に、またゼロからやり直しとなってしまうという問題があります。
最初は不要だと思っていたが、あとから社内システムや倉庫管理システムと接続する場合も、拡張要件やセキュリティ要件が見合わない場合、またゼロからの構築か、そのまま成長がストップしてしまいます。もしも別のシステムに乗り換え再構築となると、結局はコスト高となることに。
また、買い切りのインストールパッケージでオンプレミスの運営をする場合に、定期的なアップデート、セキュリティパッチを怠ったことでECサイトが老朽化したりセキュリティホールから情報漏洩が起こる事件がよく報告されており、社内でシステム管理者がいない場合の利用はお勧めできません。
使いやすく思えたが実際には多くの追加作業が必要だった
製品説明を読む限りは使い勝手がよく、ECに求められるすべてが含まれるように思ったが、実際には自社に必要な機能が欠けていたため運用が楽にならない、ということもよくあります。
ECプラットフォームとしてのUIは使いやすくても、使い始めてみると大量の商品管理や顧客管理をバッチ処理できなかったり、発送手配を1つ1つ手作業するなど、エンタープライズには向かない場合も。
他にも、広告からのランディングページは効率的に運用できても、ECサイト本体の運営は別途開発が必要だというケースや、自由にデザインをカスタマイズできると思っていたら、多くの制約があり、それに縛られてしまうということもあります。
このような隠れたデメリットは、宣伝文だけで判断するのは難しいため、仕様を詳しく調べ比較するようにしましょう。
エンタープライズでのプラットフォームは、さまざまな自動化が可能です。運用作業にどれだけ効率化が可能な機能が用意されているか、事前に確認してください。
固定費を甘く見積もりランニングコストが高額になってしまった
ECサイトのランニングコストには、ECプラットフォーム利用代金、オンプレミスではサーバ代金、人件費、そして決済手数料などがあります。これに加え、商品管理、倉庫管理、配送料などもかかります。
ECプラットフォーム利用代金は、どれだけの機能をどんな月額費用で使えるのか、利用上限などがないか、項目をしっかり確認することで、追加のコストがかかることを防ぎましょう。初期費用はかからないサービスも多くなっており、SaaS型ではサーバ代金が含まれているのが通常です。すべて自社スタッフが更新するのか、コンサルタントや制作会社に外注するかによってもランニングコストは異なります。
エンタープライズでは、成長に従って販売件数が増えるため、決済手数料が成長の足かせとなる場合が多くあります。
また、人件費は、バックエンドの作業や商品管理、マーケティングなどを行うために、どの程度の手間がかかり、専属のスタッフが必要かによって異なります。正社員・自社でバックエンド作業をするよりも、外注化する方法や、システムで自動化できるかも考えてみましょう。そういった連携・自動化ができなければ固定費は売上につれて上がってしまい、最終的には利益を減らしてしまう要因となりかねません。
社内の要望を取り入れようとして起ち上げに時間がかかりすぎてしまった
予算もある程度大きめの自社EC起ちあげなどで、社内の要望をすべて取り入れてサイトを起ちあげようとして、うまくいかなくなってしまうケースもあります。
世間一般のD2Cは準備期間が1〜2ヶ月など、非常にスピーディな動きで成功しました。いわゆるアジャイルスタイルに近く、設計を固めてから開発に入るといったウォーターフォールとは異なるスタイルで開発・運営を進めているのです。
また、設計優先のEC構築プロジェクトでは、機能定義から固めようとしても、候補となるプラットフォームに特定の機能が無いなどで独自開発が増えてしまうこともあります。D2Cプラットフォームに無い機能は無くても進められるかなど、柔軟に対応できる社内状況にないと、高性能なプラットフォームを選んでも、なかなかその良さを生かせなくなってしまいます。
→D2CのECサイト構築もおまかせ。BiNDecがオンラインにてご相談を承ります。
D2Cの成功事例
ここでは、日本で成功を遂げているD2Cの運用事例を2つ紹介します。
オリオンビール

オリオンビールは沖縄県のビールメーカーで、公式通販サイトのリニューアルに際してShopifyを導入しました。システム面で拡張性が高いShopifyは、ユーザーにも必要なときに、注意点などを示すことができます。
導入によって、受注から出荷までのプロセスがスムーズになっただけでなく、サイト全体の利便性が向上したことも大いに売上に貢献しています。
グリーンパン

グリーンパンは、ベルギー発祥のフッ素樹脂を使用しない調理器具ブランドです。フッ素を使用しないため、人体や環境にやさしい作りとなっており、これが人気の秘訣でもあります。とりわけThermolon(サーモロン)は特許を取得しているセラミックコーティングで、コアなファンからの人気も高くなっています。
公式サイトから別サイトに移動することなく直接購入できるのが魅力のひとつですが、こちらはBiNDecで構築を支援しShopifyを導入しました。
→D2CのECサイト構築もおまかせ。BiNDecがオンラインにてご相談を承ります。
D2Cを始めるのにShopifyがお薦めできるわけ
D2Cは、スタートアップのみの流行レベルを超えて、企業各社が取り組むべき顧客とのチャンネルと捉えるべきです。
メーカーであれば卸販売ではできないロイヤルカスタマーとの接点づくりが可能なチャンネルとして、ブランドであれば、よりブランド力が高く利益率も高い販売チャンネルとして、そして新興企業や海外などへ進出したい企業にとっては、D2Cがメインの販売プラットフォームとなっていきます。
D2Cをスタートする際は、売上到達目標はあったとしてもどこまで伸びるかは関係者にとっても未知であるため、開発に時間がかかるのも初期コストが多くかかるのも非常にリスクとなるでしょう。一方で、あまりに手軽なサービスやパッケージで始めてしまうと、ある程度様子がわかって成長期に入ったときに、頭打ちになってしまうことも。
ですから、個人レベルでも運用できる低コストから始められるのに、1分に1万件を超える決済まで可能なスケーラビリティを提供することができるShopifyは、成長を見越して柔軟に対応することが求められるD2Cにお薦めのサービスです。
Shopifyで作るならBiNDecに相談
D2CのECプラットフォームとしてお薦めのShopoifyですが、その拡張性やカスタマイズ性などから、どう使うかで迷うこともあるでしょう。また、普段の運用はEC担当者で対応できても、拡張や追加機能に関しては、相談できるパートナーを持っていることが理想的です。
例えば世界的に人気があるShopifyは、単体での利用よりも、BiNDecを導入することで、ブランドイメージにあわせてカスタマイズされたクオリティの高いECサイトを構築できます。また、Shopify Plusパートナーに認定された豊富な実績をベースとした運用コンサルティングで、ECサイトの売上を伸ばすことが可能です。
BiNDecのオンライン相談に申込む