
- 事例
インバウンドと越境EC|グローバルに和の文化を届けるアパレルブランド火消魂
インバウンドとShopifyによる越境ECで世界中にファンを持つアパレルブランド火消魂(HiKESHi SPiRiT)の佐藤 寿洋氏にインタビュー。海外市場への戦略と成功の理由を探ります。

インバウンドとShopifyによる越境ECで世界中にファンを持つアパレルブランド火消魂(HiKESHi SPiRiT)の佐藤 寿洋氏にインタビュー。海外市場への戦略と成功の理由を探ります。

発売前の商品や、現時点で在庫がない商品の注文を予約として受付け、発売日や再入荷後に購入者に発送する「予約販売」をShopifyに導入するためのアプリやポイントを解説します。

インスタのショップ機能は投稿からECサイトへの誘導が可能な、EC事業者にとって魅力的な機能です。ショップ機能の導入方法や注意点、Shopifyとの連携がおすすめな理由や方法を解説します。

Shopifyの公式生成AI機能であるShopify MagicとSidekickは、EC事業者の負担を軽減し、ビジネスを大きく飛躍させるために開発されたツールです。今回は、それらの機能を深掘りして解説します。

ECサイトを運営する中で欠かせない帳票の領収書ですが、Shopifyには領収書作成機能は組み込まれていません。そこで、Shopifyで作成したECサイトで領収書を発行する方法と領収書発行にまつわるFAQを併せて紹介します

ECサイトの集客や購入、リピーター獲得に欠かせないマーケティング施策。ECや顧客の状況に合わせて実施したい14施策を、Shopifyで実施する機能やアプリを含めて紹介します。
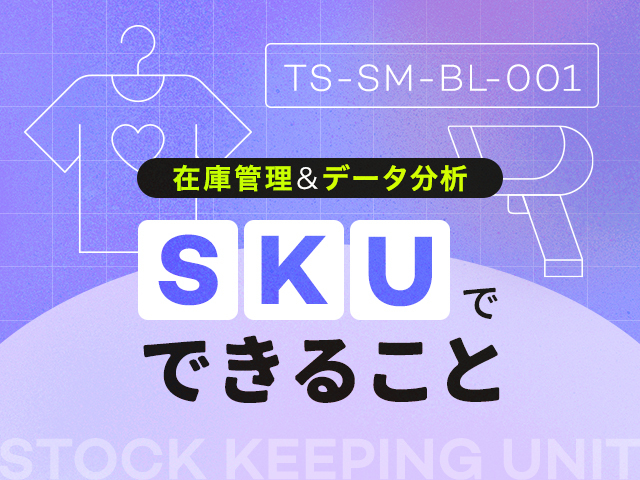
ECサイトの在庫管理に役立つSKUコードについて、メリットや設定すべきケース、注意点などを紹介します。SKUを設定することで販売データの分析、顧客管理の改善にも繋がります。
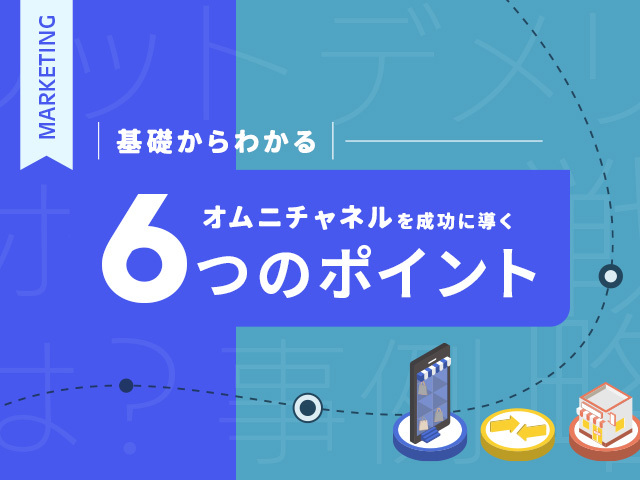
オムニチャネルとは、企業と顧客をオンラインとオフラインを問わず全てのチャネル(経路)で結ぶことです。活用できれば、販売の機会損失をはじめ、さまざまなメリットがあります。

最近のASPカートではアプリなどで機能拡張することで、エンタープライズ企業でも十分に満足のいくECサイトの構築が可能になっています。ASPカートのメリットや選び方のコツなどをご紹介します。

ECサイトのリプレースの際、カラーミーショップからShopifyへ移行を考えている事業社向けに、カラーミーショップとShopifyの違いに触れながら、移行の準備やポイントをまとめました。

日本とベトナムで行うBiNDecのShopifyストア構築プロセスについて、フロントエンドエンジニアリングチームのメンバーに技術面や対応面での工夫や試行錯誤をインタビューしました。

Shopifyでは、多くカスタマーのニーズに対応するために決済方法を拡張できる外部サービスがあります。大手企業のECの利用率も高い決済代行サービスKOMOJUについて紹介します。

ECで“成功”するには「トレンドに乗っていること」も大切。そこで、近年のECサイトのトレンドについて解説し、注目の最新事例や実施施策を業界ごとに紹介します。ご自身の業界はもちろん、他の業界もぜひ参考にしてください。

Shopifyでは、標準機能でクーポンを発行できます。売上アップや顧客ロイヤルティの向上にも効果的なクーポン機能の使い方、発行の注意点なども併せて解説します。
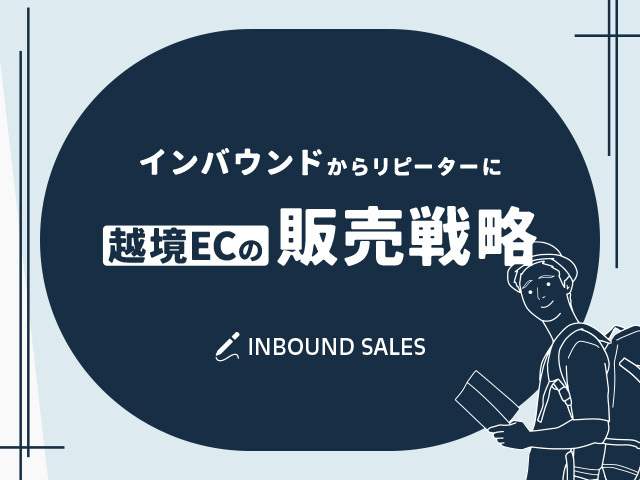
訪日外国人観光客によるインバウンド消費が増加するなか、帰国後も越境ECへ繋げようという動きが出ています。インバウンド需要と、日本ファンに向けた海外へのマーケティングについて紹介します。

Instagram(インスタ)に投稿した画像や動画をShopifyで構築したECサイトに埋め込むメリットや、その方法、便利なアプリなどについて説明します。

生活に密着した「食品」を扱うECには、賞味期限など通常の商品を扱うECサイトとは異なる課題ポイントが。食品ECサイトの運営を検討している方向けに、成功のポイントや課題、食品をECで取り扱うメリットなどをご紹介します。

ECサイトの売上向上のために、KGI、KPIを設定することは必須といえます。ECサイトの目標を達成するために見るべき数字をしっかり把握するためのポイントと、その後の施策について例を挙げて解説しています。

マーケティングWeek−夏 2024−に、ECプラットフォームのShopifyが出展。ブース内のセミナーエリアにてWEBLIFE 代表の山岡が登壇し、ECのグロースについて事例を交えてお話ししました。

makeshopからShopifyへ移行を考えているEC事業社向けに、makeshopからShopifyの違いに触れながら、移行の準備やポイントをまとめました。

NRF 2024: Retail’s Big Show Asia Pacific(NRF APAC 2024)にて展示されていたShopify POSや、越境EC、ユニファイドコマースを促進するためのソリューションを紹介